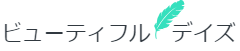白血病には種類があるの?
どんな種類の白血病があるの?
そんなあなたの疑問を解決します。
多くの人が ひとくくりに「白血病」といっていますが、白血病にはさまざまな種類があります。
 アルノ
アルノ例えば、私の妹が患った「白血病」は「急性 骨髄性 白血病」であり、急性骨髄性白血病におけるFAB分類の「型(かた)」は、「M6」=赤白血病になります。
今回は、この白血病の種類について、簡単にわかりやすく説明します。
【実質半額】楽天市場 スーパーDEAL
\毎日更新。50%OFFで入院前、治療中のショッピングに役立つ /
1)骨髄性?リンパ性?
白血病は がん化した細胞がどこで増殖するかによって「骨髄性」と「リンパ性」に分かれます。
日本で多いのは「リンパ性白血病」より「骨髄性白血病」が多く、さらに「慢性」より「急性」が大半を占めていると報告されています。
また子供の場合、小児の死因で一番多いのが「小児がん」ですが、小児がんの中で最も多いのが「急性リンパ性白血病」です。
2)急性?慢性?
さらに病気の進行パターンや症状から「急性」と「慢性」に分けられています。
急性か慢性かを考えるときに大切なことが「急性」と「慢性」は全く異なる病気だということです。



「急性白血病は、慢性白血病が突然悪化したの?」「慢性白血病は、急性白血病が長引いた状態のこと?」という声があったので念のため。
急性白血病
急激に白血病細胞が増えて正常な血液が造れなくなり、正常な赤血球、白血球、血小板の数値は減っていきます。
進行が急速なので、治療をほっておくと命の危険があります。
慢性白血病
血を作るモトとなる造血幹細胞の遺伝子が傷つき、造血コントロールできなくなった結果、がん化した血液細胞が無制限に増殖し白血球の数は増えます。
進行はゆっくりで、初期症状はほとんどありません。
3)白血病の分類法
白血病の世界的な分類法には、FAB分類とWHO分類があります。
なるべく簡単に説明しますね。
1.FAB分類
フランス・アメリカ・イギリスの研究グループ(French‐American-British)によって1976年に提唱されました。
血液腫瘍の代表的な分類法として世界的に普及しています。
骨髄中の細胞全体の中で白血病細胞(芽球ともいう)が30%以上で急性白血病と定義します。
2.WHO分類
新しい白血病分類法として、200年にWHO分類ができ、さらに新しい版が発行され続けています。
WHO分類では、骨髄中の白血病細胞(芽球)の比率が20%以上で急性白血病と定義されます。
白血病の種類


1.急性骨髄性白血病(AML) FAB分類で8つにわかれている
急性骨髄性白血病とは、骨髄系の造血細胞が悪性腫瘍化し、分化・成熟能を失う疾患です。進行が速く、正常な血液細胞が作られなくなることによる症状が現れます。
FAB分類では以下の8つの種類にわかれています。↓
- M0-急性未分化型骨髄性白血病
- M1-急性未分化型骨髄芽球性白血病
- M2-急性分化型骨髄芽球性白血病(比較的予後は良好)
- M3-急性前骨髄球性白血病(予後良好)
- M4-急性骨髄単球性白血病(M4Eo は予後良好)
- M5-急性単球性白血病
- M6-赤白血病
- M7-急性巨核芽球性白血病
こちらの記事も参考になります。


急性リンパ性白血病(ALL)
急性リンパ性白血病(ALL)は、リンパ球になる前の細胞に異常が起こり、がん化した細胞(白血病細胞)が骨髄で無制限に増える病気です。
急性リンパ性白血病(ALL)は、FAB分類ではL1からL3までの3型に分類されます。(現代では、L1とL2との形態学的な分類は臨床的意義に乏しいとされている)
- L1-小児型のALL(予後良好)
- L2-成人型のALL
- L3-バーキッド型
WHO分類では、ALLは骨髄を主病変とするリンパ系悪性腫瘍であり、リンパ芽球性リンパ腫(lymphoblastic lymphoma:LBL)と同じカテゴリーに分類されます。
主に前駆細胞性リンパ腫瘍として、、
①特異的染色体異常を伴わないBリンパ芽球性白血病/リンパ腫、
②特異的染色体異常を伴うBリンパ芽球性白血病/リンパ腫、
③Tリンパ芽球性白血病/リンパ腫
この3つに分類されます。
3.慢性骨髄性白血病(CML)
慢性骨髄性白血病(CML)は、造血幹細胞が異常になり、白血球や赤血球、血小板の数が無制限に増える病気です。
BCR-ABL1融合遺伝子があることが主な特徴で、症状が比較的軽いためぐうぜん健康診断で発見されることがあります。


4.慢性リンパ性白血病(CLL)
慢性リンパ性白血病(CLL)は、成熟した小型のBリンパ球が悪性化し増殖する病気で、骨髄やリンパ節などに腫れを引き起こす白血病の一種です。
非常にゆっくりとした経過をとることが多く、一般的には50歳以降の中高年に多く、女性よりも男性に多いという統計があります。
成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)
成人T細胞白血病・リンパ腫(ATL)は、HTLV-1ウイルス感染が原因でT細胞が悪性化し、全身のリンパ組織や臓器に転移する白血病または悪性リンパ腫です。
骨髄異形成症候群(MDS)から移行した急性骨髄性白血病(AML)
MDSと同様に、骨髄に異常な幼若な造血細胞が増え、正常な造血ができなくなる病気です。しかし、AMLはMDSよりもさらに幼若な細胞が増え、悪性化した細胞が骨髄や血液に急速に広がるため、急性白血病に分類されます。
二次性白血病(抗がん剤の治療後に発症)
二次性白血病は、他の病気や治療によって発症する白血病のことを指します。
例えば、化学療法や放射線治療などのがん治療が原因となる治療関連白血病や、長期間の免疫抑制治療による感染症後に発症する感染関連白血病があります。
また、先天性疾患や染色体異常が原因となる先天性免疫不全症候群やダウン症候群、化学物質や放射線などの環境因子が原因となる環境関連白血病もあります。



二次性白血病は、急性白血病と慢性白血病の両方があり、治療法はそれぞれの種類や原因によって異なります。
まとめ
以上、白血病の種類である「骨髄性」か「慢性」か、「急性」か「慢性」か、さらにFAB分類によるタイプを紹介しました。
このように白血病の種類は、大きくわけると「骨髄性」・「リンパ性」・「急性」・「慢性」の4つのタイプに別れ、さらに詳しい分類法で治療法や予後が分別されています。



ここでは「誰でもわかりやすい」ことを目指しているため、分類の説明である「芽球のペルオキシダーゼ陽性率」など医療専門用語での説明は省いています。
ネットで白血病を検索していても、さまざまな病名が目に留まるのは、分類によって白血病の種類が細分化されているのだ、という理解でひとまずはよいと思います。
このように、「白血病」といっても、多くの種類に分かれています。
なぜこんなに たくさんの種類に分けなければならないのでしょう?
それは、分類することによって、それぞれの病気にあった治療スケジュールや、治療に使う薬、移植のタイミング、再発しやすいかどうかの判断に役立てるためなのです。
そのため、分類法は改定が行われ続け、その精度を高める研究がなされています。
白血病の種類については、どのタイプの白血病なのか、FAB分類の「型」は何か、その簡単な意味を知っておくことは、全体的な治療の方向性を知るうえでも重要です。
▼『白血病』と診断されて、はじめに知っておきたい情報はこの記事でまとめています。
▼入院準備品のリストはこちらの記事が参考になります。元看護師目線でわかりやすく、本当に必要なものやポイントがわかります。


まずは、どこでもいい、旅にでてみませんか?
病気の回復をねがたり、闘病をのりこえた記念に、旅を計画するもおすすめです。
人生は一度きり、同じ日は二度とやってきません。
わたしの人生を大きく変えてきたのは、知らない土地への旅がきっかけでした。出会った人、街の雰囲気、異なる文化の体験が、自分の人生をまるごと変えるパワーを「旅」は持っています。
旅の計画におすすめなのが 楽天トラベル 。圧倒的にポイントがたまりやすく、期間限定のクーポンや、日本国中の宿泊施設が豊富です。きれいな景色を見たり、おいしいものを食べたり、温泉にはいったりして、ゆったりと癒されることを願っています。
あなたの大切なひとも、あなたも、一日の始まりには「今日も美しい日だ」と思えますように。アルノ