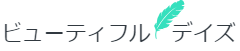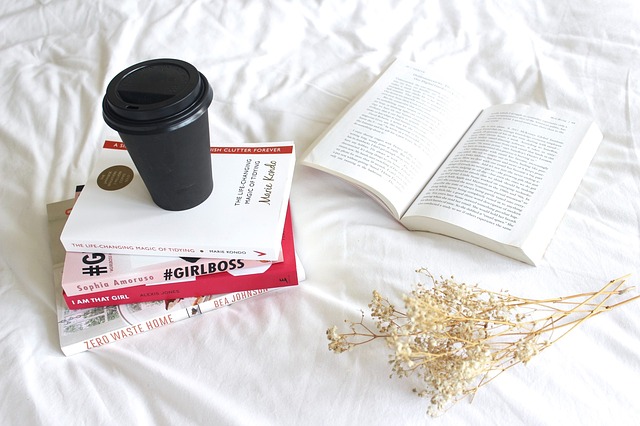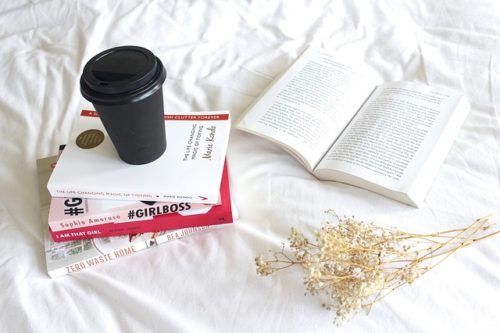白血病の治療ってどんなことをするの?
白血病の治療法には、「1.抗がん剤治療(化学療法)」、「2.(骨髄)移植」、「3.支持療法」の3つの治療方法があると言われています。
この記事では、化学療法、移植、支持療法という3つの白血病の治療法について紹介します。
白血病の治療がはじまる前にぜひ参考にしてください。
 アルノ
アルノ記事を書いているのは、イギリス在住で元看護師、白血病を患った妹のドナーとなった経験のあるアルノです。治療方法を事前にしることで、余計な不安を減らすことができます。
【実質半額】楽天市場 スーパーDEAL
\毎日更新。50%OFFで入院前、治療中のショッピングに役立つ /
1)抗がん剤治療(化学療法)
抗がん剤治療とは、白血病のがん細胞をなくすために抗がん剤を投与し、白血病細胞の増殖を抑える治療のことです。
白血病細胞が消滅する寛解(かんかい)を目指し、非常に強い大量の抗癌剤で治療を行います。
寛解導入療法により完全寛解を目指し、がん細胞を徹底的にたたき、、寛解すると次は地固め療法、そして経過をみて維持・強化療法となります。
この間、一時退院などもあるのでずっと入院しているわけではありません。



骨髄移植をおこなわず、抗がん剤治療のみの場合もあります。
①寛解導入療法(かんかいどうにゅうりょうほう)
寛解導入療法とは、化学療法や放射線治療の前に行われる治療です。
がん細胞をより効果的に攻撃するため、薬剤や放射線をより効率的に働かせることを目的としています。
治療期間の目安:だいたい3~6週間かかる
②地固め療法(じがためりょうほう)
1コース約1か月×数回行われる。
治療期間の目安:約4か月ほど
③維持・強化療法
治療期間の目安:数ヶ月~数年かかる



寛解(かんかい)とは白血病細胞が血液や骨髄の中から姿を消した状態のことです。治療で必ず聞く重要な単語です。
寛解についてこちらの記事でより詳しく説明しています。医師との病院説明でも重要な言葉なのでぜひ参考にしてください。
抗がん剤の副作用については、こちらの記事が参考になります。
どの時期にどんな副作用が現れるのかは予想がつきます。抗がん剤の副作用を少しでも和らげたいと思っているかたは ぜひ読んでみてください。
▼抗がん剤の副作用で起こるつらい思いをすこしでも避けるため「あなた自身ができること」について紹介しています。化学療法をうける方やそのご家族、友人のみなさん、ぜひ参考にしてください。
▼医療ウィッグについてはこちらの記事が参考になります。
2)(骨髄)移植
『移植』は、白血病を完全に治療することを目的に行われます。
移植治療は、ドナーから正常な骨髄(造血幹細胞=血を作るモト)を移植し、造血機能を回復させる治療方法です。
移植は、次の症例などで治療が検討されます。
- 抗がん剤治療で寛解に至らない場合
- 完全寛解したが再発が高率で予想される場合
- 寛解後に再発した場合
- 抗がん剤が効きにくいとされる白血病のタイプ
【骨髄移植】について、最初にわたしが知りたかった8つのことについての記事もぜひ参考にしてください。これを読めば、骨髄移植がどんな治療なのかがわかります。
【末梢血幹細胞移植】について最初に知っておくべきことを10のポイントで紹介しています。末梢血幹細胞移植を考えている人はぜひ参考にしてください。
3)支持療法(しじりょうほう)
支持療法とは、抗がん剤治療や移植によっておこる感染の危険を防ぐことを目的に行われる治療です。
抗がん剤治療や骨髄移植は、「骨髄抑制(こつずいよくせい)」といわれる治療の副作用が出現します。
この骨髄抑制の時期は、副作用にる骨髄の働きの低下により赤血球、白血球、血小板の数が減少、それに伴い非常に感染しやすい状態になるのです。
支持療法の例としては、、
- 無菌室での管理
- 抗菌薬の予防投与などの感染の予防
- 血小板や血小板の輸血
- 口の中や肛門まわりの清潔
- 吐き気止め薬や輸液による栄養管理
- 精神的ストレスに対するケア
このような化学療法や移植療法と合わせて行われる一連の療法を支持療法といいます。とても大事です。



抗がん剤で起こる副作用を軽くしたり、白血病の合併症に対処するための治療が支持療法です
まとめ
以上、白血病の3つの治療方法である『抗がん剤治療』、『骨髄移植』、『支持療法』について紹介しました。
白血病の治療は、白血病の病型、年齢、進行状況など本人の状態に応じて、患者それぞれにあわせた治療が行われます。
治療法を知っておくことは、これからおこる様々な治療に精神的についていけるようにするためにも大事なことです。
妹の場合、「急性骨髄性白血病」と診断され、抗がん剤が効きにくいとされる「M6」と呼ばれる型だったため、最初の段階ですでに骨髄移植を視野にいれた治療スケジュールが組まれました。
それは、『まず抗がん剤で白血病のがん細胞をなくして完全寛解したうえで、造血幹細胞移植を行う』、という治療内容でした。
⬇入院準備ならこちらの記事で全リストがわかります。元看護師のわたしならではの目線でつくったリストです。ぜひ参考にしてください。


まずは、どこでもいい、旅にでてみませんか?
病気の回復をねがたり、闘病をのりこえた記念に、旅を計画するもおすすめです。
人生は一度きり、同じ日は二度とやってきません。
わたしの人生を大きく変えてきたのは、知らない土地への旅がきっかけでした。出会った人、街の雰囲気、異なる文化の体験が、自分の人生をまるごと変えるパワーを「旅」は持っています。
旅の計画におすすめなのが 楽天トラベル 。圧倒的にポイントがたまりやすく、期間限定のクーポンや、日本国中の宿泊施設が豊富です。きれいな景色を見たり、おいしいものを食べたり、温泉にはいったりして、ゆったりと癒されることを願っています。
あなたの大切なひとも、あなたも、一日の始まりには「今日も美しい日だ」と思えますように。アルノ